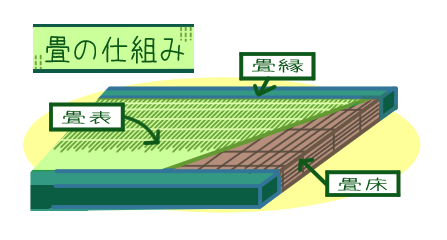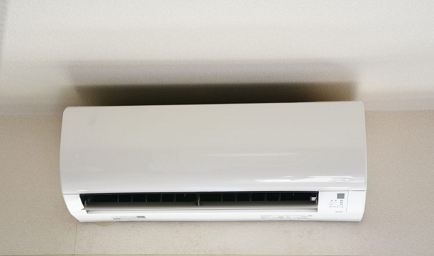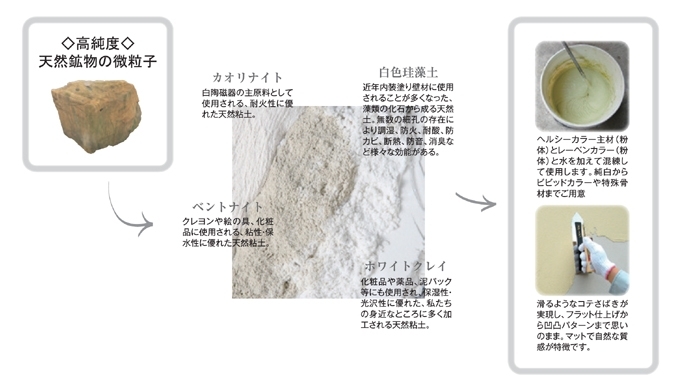緑のある生活
5月も中旬から下旬にかけて、新緑のまぶしい季節となりました。
公園などに散歩に出て、緑を感じるのもよいですが、
家の中にも緑があると落ち着きますよね。

そこで今回は家の中に置く観葉植物の選び方や
おすすめの植物についてのお話です。
育てやすい観葉植物
観葉植物にも、環境に適応しやすい丈夫なものもあれば、
環境の変化に敏感で繊細なタイプもあります。
せっかく置くなら枯らさずに育てたいですよね。
そこで、はじめてでも手入れが楽な観葉植物をご紹介します。
★パキラ

手のひらを広げたように葉っぱをつける観葉植物です。
暑さ寒さ乾燥に強く日陰でも直射日光が当たっても元気に育つため
置き場所を選ばず初めて植物を育てる方におすすめです。
病気になりにくく、長持ちし生命力が高い観葉植物です。
★ポトス
淡黄色の斑模様のある艶やかな卵型の葉印象的なつる性の観葉植物です。
枯れてしまいそうになっても復活する生命力の強さが魅力です。
高温多湿の環境を好むので、明るい日陰において、
水切れがおこらないように育てるといいでしょう。
★モンテスラ

ハワイでは「希望の光を導く植物」と言われ、金運アップと名高い観葉植物です。
葉っぱに独特の切れ込みが入った個性的な形をしています。
光が少ない日陰に強く、やや湿潤な環境を好むので、
日当たりが悪くて湿気がこもりやすいような室内でも元気に育ちます。
★ガジュマル

沖縄では精霊ギジムナーが宿る木と言われ、
大切に育てると、福を運んでくれる縁起がいい観葉植物です。
気根と呼ばれる根っこが特徴的で個体差のあるビジュアルが楽しめます
幹に水を貯めているので乾燥に強く、水やりも控えめいいので
お世話しやすく、植物初心者の方にもおすすめです。
小さめサイズの観葉植物
観葉植物は品種の珍しさや大きさなどによって値段が様々です。
始めたばかりで高いものを買って、育てることに自信がなければ、
小さめの品種から始めてみてはいかがでしょうか。
手に取りやすい価格で手入れも楽なので、初心者さんにもオススメです。
2種類ほどご紹介します。
★シマトリネコ
一年を通して艶やかな葉っぱをつける観葉植物です。
夏にはクリーム色の花や実も楽しめます。
日当たりの良い場所を好むので、窓越しの日光に当てるのがオススメ。
空気の流れが悪くなると元気がなくなってしまう可能性があるので、
湿気がこもる時期や夏場は、扇風機などで風通しを作ってあげましょう。
★ペペロミア・サンデルシー(スイカペペロミア)

スイカの皮に似た葉柄が入った特徴的な観観葉植物です。
多肉質な葉や茎をしており、お世話しやすく初心者にもオススメです。
一年を通して明るい日陰を好みます。直射日光に当たると葉焼けするので、
レースカーテン越しの光で育てるのがよいでしょう。
逆に暗すぎると枯れる恐れもあるので気を付けましょう。
広い場所に最適!シンボルツリー
小さい観葉植物は可憐でお世話もしやすいですが、
迫力のある大きな観葉植物は、一つあれば絵になりますし、
自宅のシンボルツリーにぴったりです。
ここでは大型の品種をご紹介します。
★オリーブ
平和の象徴、といわれる歴史ある観葉植物です。
花や実も楽しめますので、育てがいがあります。
日当たりの良い置き場所を好むため、屋外に適しています。
ベランダに置いても強い雨風に耐えられ
シンボルツリーらしく立派に生長します。
表土が乾いたらたっぷりと水をあげましょう。
★シルクジャスミン
シルクのようなツヤのある濃いグリーンの葉をもつ人気の観葉植物です。
小さな葉がたくさんついてボリュームがあります。
甘い香りのある白い花を咲かせ、その後可愛らしい赤い実をつけます。
名前にジャスミンとついていますが、
香料やお茶でおなじみのジャスミンとは別の植物になります。
シルクジャスミンは日当たりの良い環境を好みますが、
夏の直射日光に当たると葉焼けすることもあります。
逆に夏以外では、直射日光の当たる環境で育てることも重要です。
★エバーフレッシュ

涼しげな小さく細長い葉が整列した特徴的な観葉植物です。
1シーズンで倍以上の背丈になるのも珍しくありません。
夜になるとサワサワと動き出して葉を閉じる「睡眠運動」を行い、
朝になるとまた開く不思議な性質も魅力的。
環境に順応する能力が非常に高いので、日当たりを好みますが、
ある程度の日陰においても育ちます。
幸運を呼ぶ観葉植物
先ほど紹介したガジュマルやモンテスラにもあったように
幸福を呼ぶ花言葉や縁起の良い要素があります。
一番最初に紹介したパキラには「快活」「勝利」の花言葉がありますが
別名「MoneyTree(発財樹)」とも呼ばれ金運アップの効果もあります。
そこで、ここでは縁起のいい観葉植物をご紹介します。
★コーヒーの木
コーヒー豆が収穫できる常緑低木で、その幼木が観葉植物として人気です。
葉に美しい光沢と波打った丸い葉が特徴的です。
部屋に飾ると、金運や仕事運アップの効果が期待できると言われています。
寒さや強い日差しが苦手なので、基本的に明るい室内で育てます。
多湿が苦手なので、春~秋にかけては、土が乾いてから水やりし、
冬はさらに水やりの頻度を控えめにしましょう。
★オモト
オモトは感じで書くと「万年青」、どんな環境でも青々しく元気であることから
長寿祝いや開業祝などで贈られる縁起のいい植物として親しまれています。
自然界では木漏れ日の中で生長するので、半日陰の場所で育てます。
玄関に置けば悪い気を持ち込まないとされています。
★金のなる木

縁紅弁慶や花月といった別名のある金のなる木。
学名はクラッスラ・オバタといいます。
ぶっくりとした葉が特徴的な乾燥にも強い観葉植物です。
その名の通り、「富」「一攫千金」「幸運を招く」といった花言葉があり
縁起がいいことで人気です。
また、葉に5円硬貨を通して生長させた金のなる木を昔よく見かけました。
昭和初期の頃、栽培業者がお金がなっているようで縁起がいいということで
販売したことがきっかけだったようですが、
実際は、段々枝が太くなって成長障害を起こすので、
5円を入れることはあまりおすすめしないそうです(^▽^;
______________________
いかがでしたでしょうか?
様々な種類がある観葉植物、
何を置くか考えるだけで楽しそうです。
値段や育てやすさ、大きさやデザイン、さらに縁起物など
自分にぴったりのものを見つけれるといいですね!
______________________
「そろそろお家を建てたいな」
そう思ったら、お気軽にお問合せください^^
◆ホームページからのお申し込みはこちら
ここをクリック
◆お電話からのお申し込みはこちら:0955-58-8886
◆LINE公式アカウントからのお申込みはこちら(^^♪

https://lin.ee/eV2xSOE